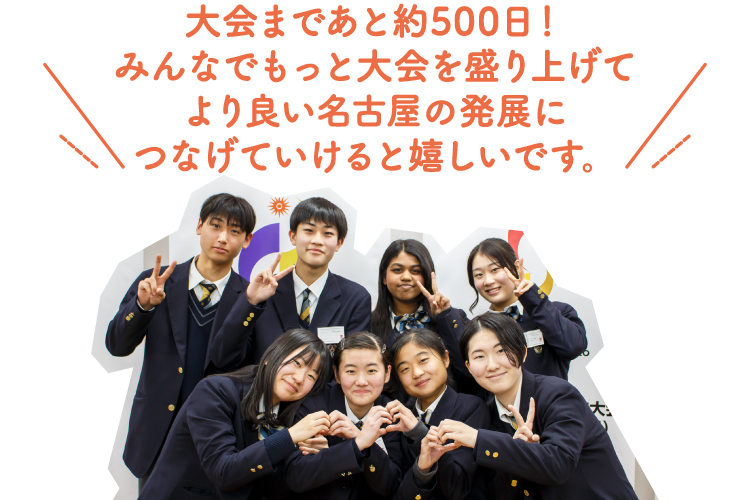いよいよ開催が来年に迫る第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会。名古屋市ではこの今まで経験したことのない規模の国際総合スポーツ大会を契機にめざすまちの姿を明らかにするNAGOYAビジョンを策定。「健康・地域活力」「魅力・誇り」「国際交流・多様性」「イノベーション・持続可能性」の4つのまちの姿を描いています。その具体的な姿を考えるべく、NAGOYAの未来を担う高校生が集まりディスカッション。4つのチームに分かれてそれぞれのまちの姿についてアイデアを出し合いました。
アジア競技大会・アジアパラ競技大会とは?
4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典。アジアの45の国と地域が参加します。

2026年9月19日(土)〜10月4日(日)
メイン会場:名古屋市瑞穂公園陸上競技場
実施競技:41競技
選手団(選手・チーム役員):最大15,000人
⇓大会の最新情報はこちら!!


2026年10月18日(日)〜10月24日(土)
メイン会場:名古屋市瑞穂公園陸上競技場
実施競技:18競技
選手団(選手・チーム役員):3,600〜4,000人
⇓大会の最新情報はこちら!!












―DISCUSSION & PRESENTATION―
高校生が考えるまちの姿1 健康・地域活力
⇒長期的なスポーツができるまち

アジア・アジアパラ競技大会のような大きな国際大会が開かれると、開催期間中はスポーツが流行することが予想されます。これを一過性のブームで終わらせるのはもったいない!
名古屋にはすでに野球やサッカーなどのプロチームがあり、実際にプレイできる施設もあるのでメジャースポーツは盛んです。しかし、マイナースポーツはまだまだ。もし大会用の施設をうまく活用できれば、子どもからお年寄りまで、だれもが自分の好きな競技を選択して楽しめる環境が整いそう。屋内施設だけでなく、緑が増え、気軽に自然のなかで運動ができるようになれば、さらに健康的です。
そして、名古屋は都会なので周りとの関係性が希薄になりがちだと日々感じています。だからこそ、アジア・アジア競技大会の開催で得たノウハウを活かし、官民が協力して学区別など小規模なスポーツイベントを開催できれば、スポーツを根付かせるとともに地域住民の交流の活性化を促し、地域活力の向上につながると考えました。
私たちにできること:SNSでの発信
発信するためにはまず自分が大会や競技について知ることが大切。発信する際は文字情報だけだとどんな競技なのかイメージがしづらいので動画を活用することで、視覚的、聴覚的に見る人の印象に残るようにしたいです。
高校生が考えるまちの姿2 魅力・誇り
⇒日本や名古屋の文化を世界に広げるまち
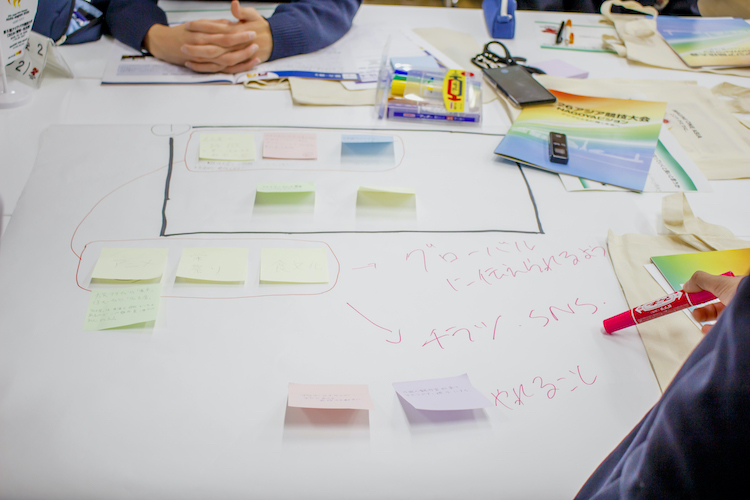
名古屋の魅力といえば、住みやすさ。都会だけれども公園が多いのでペットの散歩やスポーツが気軽にできて、自然を身近に感じられる。そういう“ちょうど良さ”が魅力なのに、海外旅行者も国内旅行者も、旅行先としては名古屋よりもまだまだ東京を選ぶことが多いのが残念。そこでアジア・アジアパラ競技大会で名古屋に来る人たちに何を発信すればその魅力に気づいてもらえるかを考えました。
手羽先、味噌カツ、台湾ラーメン…、名古屋にしかない魅力といえばやはり食文化が第一にあげられます。さらにご当地グルメだけでなく、多国籍なごはん屋さんもたくさんあるので、いろいろな場所にグルメ情報や観光スポットがわかりやすく書かれたチラシやポスターが置いてあればどんな人もウェルカムな都市になると思います。
また、いろんなお祭りやコスプレサミットのようなアニメ・マンガなどのサブカルイベントもあるのも名古屋の特徴のひとつ。休日には様々な国のイベントも行われていて、いろんな文化を体験し、尊重しあえるまちなので、「日本といえば名古屋」と思ってもらえる都市にしていきたいです。
私たちにできること:自分たちも名古屋の魅力を体験する
まずは自分たちが名古屋ならではのコンテンツやイベントを体験、その様子をSNSで発信します。また、学校でフィールドワークの授業で空港に行き、海外の方にも名古屋の魅力を伝えてみるのもいいのではという意見もありました。
高校生が考えるまちの姿3 国際交流・多様性
⇒また来たいと思ってもらえるまち

それぞれが考えた理想のまちの姿を発表しあうと、大きくわけて「グローバル化」「宗教・文化の尊重」「バリアフリー」という3つの視点があったので、それぞれ具体化していきました。
まずは「グローバル化」。名古屋は英語の看板は多いものの、その他の言語の看板は少なく、飲食店やスーパーなどではアレルギー表記が日本語でしか書かれていません。これは命に関わる危険があるので、重要な改善点のひとつです。
次に「宗教・文化の尊重」について。アジア圏にはムスリムが多くいます。名古屋市はハラルフードに対応した飲食店やモスクがありますが、もしムスリムに尋ねられてもその存在や場所を知らなければ案内することはできません。そこでそういった場所をまとめた地図があるとよいというアイデアが。
「バリアフリー」については、地下鉄の駅の改修工事などが行われ、特にトイレや手すりが充実しているなという実感があります。ですが、やはり段差はまだまだ多く、車椅子に乗る人などにとってはまだまだ不十分。もっとバリアフリー化が進んでほしいです。
最後にこれら3つの要素を達成したまちの姿を想像し、私たちが掲げるめざすべきまちの姿は「また来たいと思ってもらえるまち」と結論付けました。
私たちにできること:「興味を持つ」こと
相手がどんな考えを持っているかや何に困っているかを知ることで、お互いに心地よく過ごすことができるまちにできると思います。
高校生が考えるまちの姿4 イノベーション・持続可能性
⇒先端技術が集まり日常で使われるまち

アジア・アジアパラ競技大会を迎えるにあたって、今の名古屋に足りていないもの、必要なものを考えてみると、まず瑞穂運動場周辺の道路がレンガ調で、ぼこぼこだったりして、車椅子やお年寄りに優しくないという意見があがりました。白杖を持っているが点字ブロックから少し離れてしまって困っている人を見かけたという体験も。そこで道路を平らにするよう整備をしたり、点字ブロックと白杖がBluetoothなどで接続されて、離れたら音が鳴るシステムがあると良いなと考えました。
また、外国からやってくる人たちは110や119など緊急通報の番号を知らず、緊急時に通報できない可能性があります。例えばAEDの横にボタンひとつで緊急通報できる装置を設置することで、助けられる命が増えるかもしれません。このように大会を契機に新たな技術が開発導入され、それが日常的に使われるようになることで、みんなが安心して暮らせる、もっと住みやすいまちになると思います。
そこで、このチームでは「大会を契機に集まった様々な先進技術が日常的に使われる都市・名古屋」をめざすべきまちの姿として掲げることに。
私たちにできること:知識を蓄えて、実践を積んで、外部に発信する
アジア圏の言語を勉強したり、競技体験会に参加して、そこで経験したことをSNSで発信したりすることでアジア・アジアパラ競技大会と名古屋を盛り上げていきたいです。
オリジナル缶バッジ作りも体験しました!

大会ロゴやホノホン、ウズミンのプリントされたシートに好きな文字やイラストを書き込んでオリジナル缶バッジを作成。座談会の思い出として飾っておくと、観るたびに大会のことを思い出しますね!